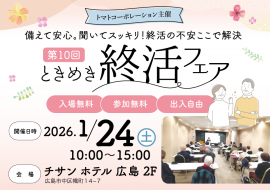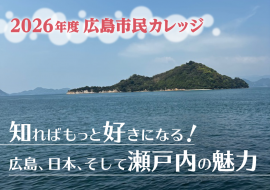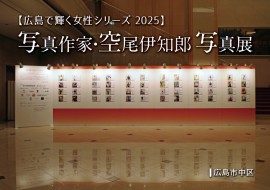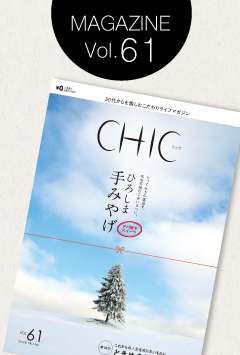おでかけやご利用の際は公式サイト等で最新の情報を確認してください。
《整理収納アドバイザーの藤田聖子さんに聞く!》今日からできる!「片付け」のコツ
おでかけやご利用の際は公式サイト等で最新の情報を確認してください。

ある片付けに関する意識調査によると、だいたい日本人の3人に2人が片付けに苦手意識を持っているとのこと。多くの人にとっての悩みである片付けについて、広島で活躍する整理収納アドバイザーの藤田聖子さんに聞いてみました。
▼この記事を読んで分かること
◎基本的な片付けの流れ。
◎家族の物を片付けるときに気を付けること。
◎モチベーションアップのコツ。
この記事を読めば、「すっきりした暮らし」を目指すためのポイントがわかりますので、ぜひ参考にしてみてください。
1. まずはどこから手を付ければよいか

片付けたいけれど、物が多すぎて何から始めればよいかわからない。
そんなときは「なんだかモヤモヤする」場所から始めてみましょう。まずは一か所片付けて達成感を味わえば、次もやってみよう!とやる気が出るかもしれません。
片付けは、何より効果を体感することが大事です。
2. 基本的な片付けの流れ
まずは「いる・いらない」に分ける
はじめに、片付けを4つの段階に分けて考えます。
①整理(分ける)
②収納(指定席を決める)
③片付け(元の場所に戻す)
④掃除(汚れを取る)
このうち、①②はライフスタイルの変化や年度末など暮らしの変化があるときに見直すこと、③④は毎日行うことと分類できます。
最初に行うのが①の「整理」。つまり、物をいる・いらないに分ける作業になります。
このときのポイントは、しまっている物をすべて出しきること。そして使っているかいないか判断することです。私がお客様の家へ片付けに行くときは、部屋の広い場所にブルーシートを広げて「全部出し」することからスタートします。
すべて出すことによって、棚の奥で忘れ去られているもの、賞味期限の過ぎた食品、壊れて使えない物など、不要品が見つかる場合があります。いらないものを分別するだけでかなりすっきりしますよ。その上で、いるものについては種類別などに分けていきます。

▲ 藤田さんが実際に行った片付け現場の写真
物の指定席を決める
次に②の「収納」。物の指定席を決めていきます。
コツとしては、使用頻度ごとに「一軍」「二軍」「三軍」などと分けていきます。たとえばキッチン用品の場合、よく使うおたまや菜箸などメジャーどころは取り出しやすい引き出しの手前へ。たまにしか使わないすりこぎや泡だて器などは奥の方へ。こんな風に使いやすく分けていきましょう。
また、コンロ周りには調理時に使うもの、水回りにはボウルやざるといった具合に、作業導線を考えながら配置していくといいですね。最初は大変に感じるかもしれませんが、進めるうちにだんだん楽しくなってきますよ。
①と②で片付けるための基準が決まれば、日々の③④がスムーズになり「すっきりした暮らし」を無理なく継続できるようになります。

3. 自分以外の家族の持ち物についての対応
まずは、家族の物を勝手に捨てることのないよう気を付けたいですね。自分にとっては価値がないように思えても、相手にとっては意外と大事な場合もあります。かといって、物があふれるようでは困りますよね。
そんなときは、持ち主に「これ、使ってる?」とたずねてみましょう。「これ、いる?」と聞くと、たいして使わない物でも「いる」と答えるかもしれません(笑)。でも、使っているかどうかは気持ちでなく事実なので、使っていないと答える可能性があります。物が増えると生活しづらいですし、年配の方にとっては身の危険につながります。快適に暮らすためには、不要なものを処分する必要があることを家族にも理解してもらいましょう。
4. 片付けのモチベーションを上げるコツ

片付けをした先の暮らしをイメージして目標にすることが、継続的に片付けをして頑張るモチベーションになります。例えば、
「コーヒーを飲みながらゆっくり読書がしたい」
「友人を呼んでお茶会をしたい」
「夢だった料理教室を開きたい」
など。すっきりしたおうちでやりたかったことをしている……その様子を思い浮かべるだけで、やる気が出てくるかもしれません。また、片付けによって物の所在がはっきりし、ムダ買いが少なくなるという経済的なメリットもあります。そして何より、片付けをすると心にゆとりが生まれ、毎日が楽しくなるということを知っていただけたらと思います。
5. まとめ
片付けのコツ
・片付けを4つの段階に分ける
・分類するときは、すべての物を出しきって行う
・収納するときは、使用頻度などによって場所を定める
・家族の持ち物は「使っているかどうか」を質問してみる
・片付けた先の暮らしをイメージして目標にする
●整理収納アドバイザー・藤田聖子さんのInstagramはこちら