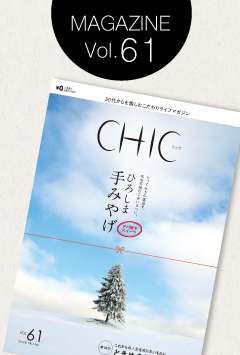今や国民病とも呼ばれる「花粉症」。
花粉症の方には辛い季節の到来ですが
2025年の花粉飛散予測は前シーズンに比べ
非常に多い見込みです。
そこで今回の市販薬のトリセツは
「花粉症」についてお話します。
Vol.51_市販薬のトリセツ~花粉症編~

●花粉症のメカニズムと症状
花粉症は、スギやヒノキなどの花粉が原因で起こるアレルギー疾患です。「季節性アレルギー性鼻炎」とも呼ばれます。私たちの体にはもともと、外部から入る細菌やウイルスを排除する働き(免疫機能)があります。そして免疫機能が細菌やウイルスを攻撃する時「IgE抗体」という物質が作られます。この抗体ができた後、再び花粉が体内に入ると、目や鼻の細胞の表面に付着しているIgE抗体と花粉とが結合し、アレルギー症状と関係する「肥満細胞」からヒスタミンなどの化学伝達物質が分泌され、それらの物質が神経や血管を刺激するのです。
花粉症の症状として主なものは、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみです。風邪の症状と異なり、くしゃみは花粉が飛散している間ずっと続き、鼻水は水のようにサラサラしているのが特徴です。また、症状が重くなると、皮膚のかゆみや倦怠感、不眠や集中力の低下など、全身症状を伴うこともあります。
●花粉症の薬の種類
花粉症の市販薬には、以下のタイプがあります。
【内服薬】錠剤・カプセル・粉薬など、さまざまです。有効成分が体の隅々に届くので、目、鼻、喉など体全体のアレルギー反応を抑えますが、効果が現れるまでに時間がかかることがあります。
【点眼薬】目のかゆみ症状に用います。目に直接投与するため、かゆみ症状には即効性を期待できます。
【点鼻薬】鼻水・鼻づまりの症状に用います。鼻に直接吹き付けるタイプの薬剤です。
また、花粉症の薬には、アレルギー反応を引き起こす「ヒスタミン」という物質の働きを抑える「抗ヒスタミン薬」が多く用いられます。「抗ヒスタミン薬」はさらに、効果が早いが眠気や集中力低下などの副作用が強い「第1世代」、副作用が少ないので日中でも使用しやすい「第2世代」に分けられます。現在の市販薬はこの「第2世代抗ヒスタミン薬」が主流となっています。この他にも、同じくアレルギー症状を引き起こす原因物質「ロイコトリエン」「PAF」を抑える薬や、鼻や目の炎症自体を抑える「ステロイド点鼻薬・点眼薬」などがあります。
●花粉症の薬の注意点
花粉症の薬には、注意すべき副作用もあります。薬の中でも代表的な内服薬では、特に眠気や集中力の低下に注意が必要です。車の運転や機械作業がある方は気をつけましょう。また口の渇きもよく見られる副作用です。この他、蕁麻疹やむくみ、頭痛、発熱、肌荒れなどが起こることもあります。前述した「第2世代抗ヒスタミン薬」でも副作用が出ないわけではありません。眼圧を高めてしまう可能性があるので、緑内障の方は服用には注意が必要です。
症状が出る前(花粉の飛散量がピークを迎える前)から薬を服用できるのも、花粉症薬の特徴です。花粉の飛散が始まる2週間前くらいから服用することで、症状を抑えられたり症状が出るのを遅らせる効果が期待できます。
なお、寛解を目指すなら、「舌下免疫療法」という選択肢もあります。スギ花粉エキスを舌下投与することで、体質を徐々に変えていく方法です。ただし、こちらは治療期間が数年に及びます。
●おわりに
疲労は自律神経を過敏にし、アレルギー反応が起きやすくなります。十分な睡眠、お酒、タバコ、香辛料を控えるなどして、まずは生活習慣を整えましょう。また、ライフスタイルはそれぞれで、花粉症の薬もそれぞれです。まずは気軽にかかりつけ薬剤師に相談してください。