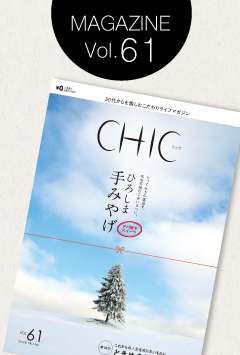毎年約4万人以上が救急搬送されている熱中症。
死に至ることもある恐ろしい症状ですが、
その背景には脱水症が潜んでいます。
今回は、暑さが増すこの時期から、
特に気をつけておきたい脱水症についてお話しします。
Vol.40_脱水症について

●脱水症ってなに?
脱水症は、体に入ってくる水分より出ていく水分が多いことで起こる状態です。汗をかいたのに水分を接種しなかったことで起こり、ナトリウムやカリウムなどの電解質は保たれているのに水分だけが不足している「高張性脱水」と、下痢や嘔吐によって起こり、水分も電解質も失われた状態になる「等張性脱水」があります。特に高齢者は、体液を多く含む筋肉量の減少、のどの渇きを自覚する感覚機能の低下、腎機能や膀胱機能の低下による頻尿、水が飲みにくくなる嚥下力の低下、食べ物からの水分・電解質摂取量が不足する食事量の減少などの理由から、脱水症が起こりやすくなっているため注意が必要です。
●脱水症の症状
脱水症になると、まずのどの渇きが生じます。また、頭痛、嘔吐、皮膚の弾力性の低下、口腔内の乾燥、汗や尿の減少、微熱、めまいなどが認められることもあります。これが重度になると、意識障害やけいれん、臓器不全なども起こり、20%の水分が失われると命の危険が高まります。高齢者では「なんとなく元気がない」といった意識の鈍化や脱水性せん妄など、発見しにくい症状が出ることも珍しくありません。
●脱水症の治療
脱水症の治療は、軽度であれば基本的に不足した水分を補うだけです。しかし、中等度や重度になると多量の電解質が失われていることもあるため、電解質と水分の両方を含んだ経口補水液や点滴によって治療を進めます。また、脱水を引き起こしている嘔吐や下痢などの病気の治療も並行して行うことになります。なお、一般に市販されているスポーツドリンクは経口補水液の十分な代用品とはならない場合があります。
●脱水症の予防
脱水症の予防でまず大切なのが、こまめな水分補給です。屋内・屋外かかわらず、のどの渇きを感じていなくても、こまめに水分をとりましょう。一般的に、成人が1日に必要な水分補給量は食事に含まれる水分を含めて2.5ℓと言われています。また、できるだけ風通しの良い涼しい場所で過ごしましょう。熱中症による救急搬送の発生場所は、4割以上が住居での発生となっています。たとえ家の中でじっとしていても空調を有効に使い、高温多湿を避けましょう。さらにコロナ禍においては、マスク着用による脱水も危惧されています。これは、マスクを着用することで体内に熱がこもりやすくなり、またマスク内の湿度も高くなっているため、のどの渇きを感じにくくなるためです。周囲と十分に距離が取れる屋外であれば、マスクを外して水分補給をすることも大切です。
●経口補水液の作り方
脱水症対策として家庭に備えておきたい経口補水液ですが、簡単に自宅で作ることもできます。材料は[水1ℓ][砂糖大さじ4杯][塩小さじ半杯]のみで、水に砂糖と塩を入れて溶けるまで混ぜるだけ。ただ、経口補水液は脱水症対策に用いるものであり、脱水症でない方が普段の水分補給として飲用するものではありません。また、ナトリウムとカリウム、ブドウ糖が含まれているため、高血圧、糖尿病の方や腎機能が低下している方は注意が必要です。必ずかかりつけの医師・薬剤師に相談してください。
●おわりに
脱水症は予防できる症状です。あらかじめ対策をしておくことで、熱中症などさまざまなリスクを減らすことができます。まずは水分補給の習慣から始めてみましょう。